 |
    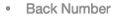   |
「シェフズ・テーブル」と題されたこのコーナーでは、 文=中村孝則 text by Takanori Nakamura 写真=堀裕二 photograph by Yuji Hori
◎生江史伸(なまえしのぶ) Dinner 18:00〜23:30(20:30 L.O) |
丸く白い皿には、主役のサーモンを中心に、モリーユ茸やアスパラガスなどでシンプルに構成されています。サーモンの下には、若草色のソースが描かれ、周りには土色の粒が散りばめられています。生江シェフによると、ノルウェーの春の大自然からイメージを構築したといいます。「黒い粒の正体はブラックオリーブで、ノルウェーの森の土を表現しています。泡には海藻とモリーユ茸のエッセンスを封じ込めました」。そう聞くと、この皿の香りがフィヨルドから漂う匂いのハーモニーのようにも思えて来ます。ノルウェーにはまだ行ったことがないという生江シェフ。イメージの核となったのは、ノルウェー産のサーモンでした。「このサーモンは、ノルウェーから生のまま日本に空輸されています。変な話ですがパリより新鮮かもしれませんね。その素材のフレッシュな持ち味を生かしたかった」。そのためサーモンには、ギリギリの火入れがなされています。口に入れると表面こそグリルしたような熱を感じますが、身の内部からは生の食感と旨味が滲みでます。食感は生だが、たしかに温かな料理を食べているという心地よさ。生江シェフの手腕が光ります。この調理のポイントは「焼かれていながらも、サーモンの水溶性のタンパク質と旨味をどう閉じ込めるかということ」だとシェフ。そのため、サラマンダー内の温度や時間、さらにはサーモンを置くボジションを微妙に調整しながら、ゆっくり調理していく。そうすることで、サーモンの表面の油は熱せられて、中心部はフレッシュな水分を逃すことなく味覚の快感の際まで温められ、旨味が引き出されます。「僕の料理は、素材ありきの料理」という生江シェフ。「何よりも素材のclarity――清澄さを大切にしたい。素材になにかをかぶせるより、切り取るイメージでしょうか」。その源流にあるのは、修業時代にミシェル・ブラスのもとで学んだ“自然への畏敬の念や好奇心”なのかもしれません。少なくとも、この一皿には、ノルウェーの混じり気のない大自然の息吹を感じるのでした。 |

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |