 |
    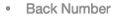   |
 |
中村孝則 Takanori Nakamura
|
 |

| サーミの村を初めて訪ねたのは、2011年の12月のことだった。僕が担当したNHK BS1「エルムンド」のノルウェー特集の中で、サーミ人のライフスタイルにも触れたいと、ディレクターの真鍋くんが企画したのだ。僕ら取材班は、トロムソからロケ車に乗り込み、さらに北の山間部へと向かった。12月の北極圏は、太陽がまったく昇らない、いわゆる極夜だ。昼の2時だというのに、もう薄暗い。トロムソから4時間ほどで、目指す村についた。気温は、マイナス15℃くらいだろうか。後から聞けば、このエリアの山あいはマイナス50℃くらいまで下がることもあるそうだ。迎えてくれたのは、このあたりの集落の長だというから、僕は勝手に“チーフ”と呼ばせてもらっていた。チーフは、奥様と小学生くらいの男の子の3人家族で、トナカイの放牧で生計をたてる典型的な山のサーミ族だ。ちなみに、サーミ人はノルウェー、フィンランド、ロシア、スウェーデンの4ヵ国にまたがって棲んでいる。またがってという言い方は適切でないかもしれない。サーミ人は、これらの国境が定まるはるか前からこの地域に棲んでいるため、そもそも国境という概念がなかったからだ。ともかく、サーミ人はノルウェーでは先住民族と認められていて、独自の議会まで持ち基本的人権も保証されている。ノルウェー国内に棲むサーミ人は、推定で6〜10万人ほどで、他の国の中でも最も多い。狩猟や牧畜で生計をたてる山系サーミ族と、漁業で生計をたてる海系サーミ族などに分かれるが、チーフはトナカイの放牧で生計をたてる典型的な山系だ。春と秋の年に2回は6000頭のトナカイとともに大移動をするそうだ。トナカイの数は、僕らでいうところの総資産にあたる。だから、彼らに「トナカイは何頭持っていますか?」と軽々しく聞くのは失礼にあたる。「銀行預金はいくらですか?」と聞くようなものだからだ。6000頭という数はかなり多いそうで、チーフも散々一緒に飲んだ後に、ぽろっと教えてくれたのだ。そのチーフの家族は、慣れないテレビカメラに緊張ぎみであったが、僕らがお土産に持参したアクアビットと葉巻のお陰で、徐々に打ち解けてくれた。焚火を囲んで、トナカイの生肉を炙りながら、地酒のアクアビットを煽ると、気分も最高だ。4時間も飲み続けると、シャイなチーフも饒舌になってきた。「そもそも日本のアイヌ族とサーミ族は、大昔からつながりがあるんだよ」という。「我々は、先住民族どうしというだけでなく、ともに豊かな音楽を持っているしね」とチーフ。そういえば最近、サーミの音楽はジャズや現代音楽の融合で、その魅力が再評価されはじめている。最近は、サーミを代表する歌手、マリ・ボイネが「サッポロ・シティ・ジャズ」に参加したのを機に、アイヌ音楽とサーミの音楽交流も盛んに行なわれているという。「よし、サーミ音楽の原点を聞かせよう」。おもむろに立ち上がったチーフは、無伴奏で歌い始めた。喉が震え焚火の炎までも揺れ出した。歌と言うより、手練の住職の読経のようでもあり、モンゴルのホーミーのようでもある。ハラワタまで揺さぶる歌声に僕らは痺れた。サーミの伝統的な即興歌、ヨイクであった。チーフが数曲ほど歌ったあと、奥様が次いで歌い始めた。女性のヨイクも不思議な高揚感がある。気がつけば、隣の真鍋ディレクターもアクアビットのボトルを抱えて恍惚と歌い始めるではないか。ヨイクはもともと、シャーマニズムに関連して生まれたというが、なるほど幽玄な雰囲気だ。みんなの顔も焚火に照らされて、まるで薪能の世界のようでもある。そういえば、この秋にサーミの劇団「国立サーミ劇場」が初来日するが、その作品は日本の能に触発されて創られたという。サーミと日本。ほんとうに、どこか遠い昔につながっていたのかも知れない。少なくとも、ヨイクをともに歌った一夜は、彼らとの不思議な一体感を味わったのであった。 |  |
族衣装をまとうサーミ人と筆者。サーミ人にとってトナカイの存在は重要だ。
サーミ族が棲む家。放牧で移動するため、すぐに取り壊せる造りになっている。
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |